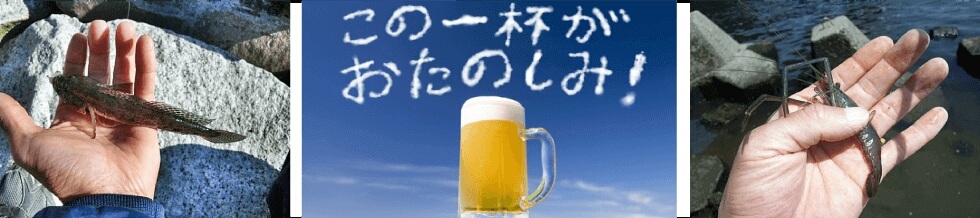2021年5回目の多摩川テナガエビ釣りは違うスポットへ
2021年5月16日
2021年五回目の多摩川テナガエビ釣りに行ってきました。
ポイント:多摩川緑地の対岸(川崎側)
天気:曇りのち雨
釣行時間:8時00分(潮位166cm下げ2分)〜10時00分(潮位107cm下げ5分)中潮
釣果:9匹(10cm〜14cm うち抱卵メスエビ2匹リリース)

竿:1.5m(大阪漁具「小魚名人」)&2.1m(シモツケ「清滝」)
道糸:フロロカーボン1.5号 ハリス:ナイロン0.3号
ハリ:タナゴ-極小新半月 ウキ:玉ウキ-ジンタン7号
オモリ:ガン球-Bとか2Bとか エサ:ミミズ
仕掛け:ハリス5cmの枝ス式二本針
この時期のテナガエビは、浅い岩陰に潜んで暮らしてる生きものらしい。
なのでそれを釣り上げるとなると、それらしい場所にエサを落とさないと釣れないということになる。
石がゴロゴロして、その石の隙間やエグレの下とかをピンポイントで狙うのである。
当然水深が数10cmくらいじゃないとエビポイントが見えないし狙えない上、深いとエビも居ないのである。
湖とか池とか水位がだいたい一定の高さなら問題ないが、オッサンが出没する多摩川の下流域は海の潮位の影響をモロに受ける汽水域。
東京湾の潮汐によってその日その時の水位が全然違うもんだから、毎回どこでテナガエビ釣りをするかは頭を悩せる大問題。
事前に潮位を調べ、ちょうど良さそうな水位のポイントを厳選して現場へ向かう。
ところが考えることは皆同じで、厳選したポイントに先客がいる事も多々ある。
近年、多摩川のテナガエビスポットは台風や護岸工事の影響で減少の一途をたどるばかり。
だもんで、テナガエビが釣れるナイスなスポットは争奪戦。
テナガエビ釣りのようにシケた釣りものをやるのは高齢者も多く、彼奴らは眠れないもんだから朝が異常に早い。
いつまでも布団でイモムシになっているオッサンが勝てるハズもない。
「おまいらリタイヤしてるんだから平日にやれよ!こちとら休日しか来れないんじゃ〜!」
と言いたくなるが、釣り場確保は早いもん勝ちがルール。
しょうがないので第二案の現場へ向かうが、そこにも後期高齢者の影が…
もうこうなると釣り場もないが、ここまで来て手ぶらで帰るのも何だし…で、ど〜でもよい全く期待できない場所で釣り糸を垂れるも本当に全く何も無いという事態になる。
本日の潮位はいつものエビスポットには高すぎて、全く釣りにならんだろう。
なので多分アソコならちょうど良さそうだけど、多分っていうか絶対に先客が来てるはずだ!
オッサンがうろうろしてるエリアは、潮位が高くても釣りになるテナガスポットはかなり限られている。
アソコまで行ってダメでの第二案は致命的なので、それならいっそのこと…
っという訳で、本日はいつもとは全く違うポイントへ向かった。
懐かしいテナガエビ釣りの聖地
本日のポイントは東京から橋を渡って反対側の川崎方面です。
まぁ、ここまでもったいつける程のもんでもなく、向かう先は多摩川のテナガエビ釣りの聖地。
東京側の多摩川緑地の対岸にあるひたすらにテトラポットが並んでいる地帯で、釣り雑誌のテナガエビ釣り特集とかでは必ず登場するエリア。
オッサン的イメージは、釣れることは釣れるんだけど別に爆釣したこともないし、テトラポットをウロウロするもんだから危ないし疲れるし、何よりも川向うなので行くのが面倒くさいという感想。
ただ、釣り場は広大なので、混んでて釣りができないということは全く考えなくて良いのはありがたい。
チンタラと愛車を漕いで橋を渡り、土手を移動してるとプ〜ン!と芳しい香りが漂ってくる。
そう川崎競馬場の練習馬場である。
河川敷にその練習馬場があり、すぐ堤内側に厩舎があるから、そこから生きものの香りがしてくる。
朝方は競走馬が練習していて、すぐ目の前で筋肉質の競走馬が走るのを見れるから、馬好きな人たちがよく見学してたりする。

ブルル、ブルルって言いながら美しい競走馬が疾走する

厩舎から横断歩道を渡って練習馬場へ。競走馬ってカッチョええ〜!
考えてみれば、夏のハゼ釣り場も目の前に大井競馬場があったりして、オッサンの釣り場って馬臭と縁が深い。
競走馬の美しい姿と匂いを堪能しながら、オッサンもブルルブルルうなりながら愛車を漕ぎ本日の現場へ。
ここは全長1km以上あるテトラ帯なんだけど、オッサンは電車の騒音が大きいからあまり鉄橋の方には行かない事にしている。

騒音を避けて手前のとこらへんにて

狙いはテトラポット間の隙間
潮位的にはちょうど良さそうだが、釣れるかどうかは別問題。
適当な場所に陣取り釣りの準備をする。
本日も自宅近くでほじくってきた3K(臭い・汚い・気持ちが悪い)ミミズがエサ。
前回やってみたらけっこう感触良かったので今回もほじってきた。

近所の公園の隅っこでゲットした野良ミミズ
準備完了にて釣り開始!
テトラ帯をピョンピョン!移動するんだけど、落ちるとドボンだし怪我するから気を付けないとね。
2本の竿を使うから置き竿になるんだけど、ここのテトラポットは丸っこい形だから安定が悪く、竿を安定させる三脚代わりの洗濯ばさみは必須。

コレが無いとず〜っと持ってなきゃならない
適当な陰に落としてウキを眺めるが、相変わらずウキがピクリともしない。
う〜ん…厳しいかな…
しかし気になるのが風である。
今日もしっかり強風が吹いてて、なんで週末になると無駄に吹くんかな〜?
更にはちょっと風が強くなると、置いてある竿がコロン!と転がって水没する。
ヒャ〜!気を付けないとなぁ〜
しばらく竿を上げ下げするが一向にアタリが無い。
ダボハゼすらも掛かってこないぞ。マジか!?
ここで粘ってもしょうがないので移動を考え始めるが、ハテ?どこへ動くべきか?
右も左も同じ様なテトラ帯なので特に代わり映えしない。
するとオッサンの鷹の目があるポイントに焦点合う。
アソコだぁ〜!!
老眼を酷使して拡大モードにすると、ず〜っと遠くに目が留まる。
ここらへんのテトラ帯とは少々趣が違うスポット。
釣り場の選定の鉄則で、他とは違う変化のあるスポットが良い釣り場になってる事が多いと思います。
そそくさと移動して眺めるとテナガエビが居付いてそうな陰がけっこうあった。
絶対いる!
ひとシーズン僅か5回程度の釣行を誇るトホホなテナガエビ釣り師の経験と勘が訴えかけてくる。
良さげな陰に2本とも落とし、荷物と愛車を移動し終えて竿を上げるとビクン!ビクン!とテナガエビの引きが!
上がってきたのはナイスサイズのテナガエビ。

やっと釣れたよ!
もう一本の竿も聞きあげるとビクンビクン!
こちらはメスだったので針を外して即リリース!

メスエビはリリースじゃ!
※メスの抱卵エビはエビ資源保護のためリリースを心がけています。できる限りで良いのでご協力お願いいたします。
移動すぐに2本とも釣れてくるとは!こりゃ〜期待しちゃうな〜
ミミズ餌も良いけれど…
俄然やる気になったオッサン。
本日は中潮で今現在、潮はドンドン引いている状態。
今がちょうど良い潮位だけど、これ以上引くと狙えるエビポイントが無くなっていく感じで時間との勝負じゃ!
っと気持ちは焦るが、脱走ミミズを追っかけたり、滑って水没しそうになるしで全然釣りにならんオッサン。
挙句の果ては蛇を見つけ、それを捕まえ始めるわでもうワヤヤ…
蛇を見つけた時は一瞬「コレって例のニシキヘビでは?」って思ってぜひ捕まえねば!と正義の人だったけど、捕まえたら1mくらいと全然サイズが違くて、そんなの見て気づけよ!って感じですね。
しかし、あの蛇も一体どこへ行ったのか知らんが、こんな河川敷まで来たらもう捕まらないだろうな…
ネズミやウサギなどのエサも豊富だし、水はあるし、隠れ家は無数にある。
あの飼い主も他に蛇やらワニやら亀やらも飼っていて全部譲渡したらしいけど、ペット飼う人って一匹じゃ済まない事が多いからな〜
会社のアホな新人も爬虫類やら珍しい昆虫類を飼っていたらしが、曰く「飽きたら河川敷に”リリース!”」とほざきやがった。
その真偽はともかく「ふざけんな!ボケぇ」と言ってやったが、こんな風に”リリース”された危ない生物がいっぱいいるんだろうな…
多摩川にもピラニアやらアリゲーターガーやらカミツキガメやらがいるし、河川敷にも毒蜘蛛が徘徊してるだろうし。
暖冬の影響で熱帯生物も日本の冬を越えて生き続けるみたいだし。
なのでオッサンはなるべく草むらには近づかないようにしています。
子どもたちも気を付けて欲しいな〜
かろうじて釣りを続けるが思ったよりも釣れないぞ。
その理由は後ほどなんだけど、時おり上がってくるテナガエビは10cmくらいの良型が多くてその引きも面白い。
少々問題なのは竿の選択を間違った事。
一本は2.1mの長さで道糸も少し長めにしてあるから問題ないけど、もう一本は1.5mしかなくてテトラ帯で使うには短すぎる。
手持ちなら問題ないけど、置き竿となるとテトラポットの上に置くことになるから水面までそこそこの高さになる。
竿が短いと当然道糸も短くなるから、本当に手前というか足元しか狙えなくなる。
もうちょっと沖のあの穴を狙いたいんだよな〜って時も多々あるから厳しくなる。
テトラ帯エリアでテナガエビをする時はやはり2mくらいの竿で道糸も長めに設定することをオススメします。

竿が短くて、バケツにこんな感じにぶら下がるしかない
多分良型が多いからなんだろうけど、今日はエビ穴内での根掛りが多かった。
明らかにエビのアタリで「来た〜!」って思うんだけど、グイグイ!穴に潜られて引きをイナしている内に根掛りで道糸プツリ!が多かった。
まぁ、強引に抜き上げても良いんだけど、エビのグイングイン!な引きが面白いからついつい遊んじゃうんですよね〜
ある時、今までにない引きと重量感で「こ、これは!?」と期待したら良型ダボハゼとエビのコラボだった。

まぁエビが付いてりゃ良しとしましょうかね
結局、2時間で9匹となんとも煮え切らない釣果でした。

まぁ、もうちょっと上がったような気もしますが…
最初からアソコでやっておけばもうちょっと数も上がったと思いますが、それは結果論で意味のないこと。
タラレバで申し訳ないのですが、これがアカムシ餌だったらもっと釣れてたと思います。
前回も思ったけど、上がってくるのが小さくても7〜8cmくらい以上ばかりでそれ以下が掛からない。
エサに喰ってくるんだけど聞き上げるとピュ〜!って逃げるから、餌だけにかぶりついて針まで届いてないということ。
細目のミミズを厳選して使ってるんだけど、やはりアカムシに比べると太いから小型エビは針まで喰ってこないんだろうな。
オッサンはミミズを1cmくらいにカットして使っています。
最初はもっと短く刻んでたんだけど、短く小さいとアピール力不足なようで1cmという長さに落ち着きました。
それ故に小エビは釣れないということですね。
まぁ、エビ資源保護の観点で言えば小型は釣れない方が良いんだけど、エサの喰い逃げは悔しいぞ!
ぐだぐだ言うくらいならアカムシ買えよ!この貧乏人が!!というご指摘ごもっともですが、やはり無料で手に入るというのは大きな魅力であります。
さらには、仮に雨が降ったりしてエビ釣り出来なければそこら辺にリリースすれば良いし、余ったズミミを捨てるのも全然もったいないと思わないので心が軽い。
反面、アカムシの場合はどうだろう?
わざわざ釣具屋に買いに行かなければならないし、本番まで妻に内緒で冷蔵庫保管。
釣行で余ったエサは心苦しく現場放流か、次の釣行まで見つからないようにと願いながらの冷蔵庫行き。
それも全て餌として使えるならともかく、半分くらいは死んでる状態。
このようにさまざまな心配をしなければならない。
いるようでなかなか見つからないズミミ様。
土からほじくり出すとピョンピョン大暴れするズミミ様。
みじん切りにすると気持ち悪い汁が出てくるズミミ様。
どこをどう見てもやっぱり気持ち悪いズミミ様。
ここら辺さえ覚悟しておけば、ミミズは優秀な釣りエサです。
追伸、ミミズって土まみれだと大人しくしてるんだけど、水っ気があると途端に動き出すので、エサ箱はしっかりフタしておかないと脱走し始める。
コレってミミズが苦しがってるのかな?
大雨の後、ミミズが地表で死んでるのを見かける事がある。
その原因は地中のミミズが大量の水分で溺れるから、というのを聞いたことがある。
確かにミミズって湿った土の中にいるんだけど、必要以上の水分だと苦しいらしい。
何だか不器用な生きものだな…