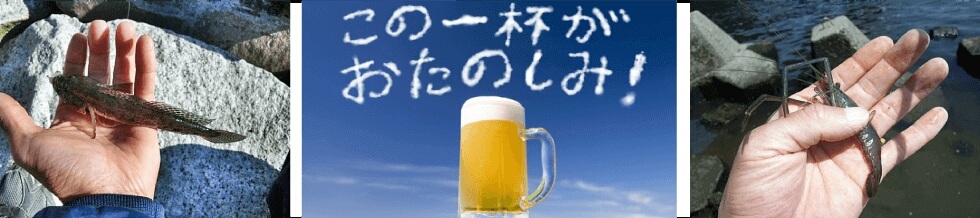夜アナゴの船釣り仕掛けを自作したんだけど以前と言っても、もう二年も前になる。船釣り専の友人オッサン2号の企画で、東京湾で夜アナゴの船釣りに行ったことがあった。前から誘われてたんだけど、オッサンはず〜っと二の足を踏んでいた。その理由は、夜の水辺に近づきたくないから。明るいうちはお洒落で人出もあるベイサイドも、夜ともなればその雰囲気は一変する。本来、海は人間の世界ではない。東京湾のように人手の入ってない場所が微塵もない港湾も、海と人間界の境界であり決して安心安全とは言えない。それが夜ともなれば殊の外である。こういう話は眉唾ものなので信じる信じないは人それぞれだけど、オッサンは”見る質(タチ)”だった。そう心霊系の話である。「だった」とオッサンは書いた。つまり、以前はよく見て感じてたけど現在は全く無いということだ。コレが歳のせいなのかは分からないけど、転機は結婚&父親になった頃くらいだったかな。子供〜若い頃はバリバリにとんがってたから酷いもんで、魑魅魍魎と同居していたという恐ろしい事実。あの頃はそれが普通だと思ってたけど、今考えるとよく頭が狂わなかったな〜とも思う。あれから数十年後の現在、人間として落ち着くと、それらも無くなり今は平和な日々でございます。とかく幼少〜若年期は何かと敏感なので気をつけたほうが良いですね。よく面白半分に心霊スポットに繰り出す若者がいるが、ここで言っておきます。絶対行っちゃダメですよ!!あ〜いう場所は質が悪いのがほとんどで、一度喰い付かれたら離れないのが多い。塩で清めるとかもらった御札に守ってもらうなんて焼け石に水で、そんなの彼奴らには蚊に刺された程度でしかありません。もう一度だけ言います。絶対に近づいちゃダメ!!面白いのはって面白がっちゃいけないんだけど、たいてい喰い付かれるのはビクビクしてる人。「全然怖かぁ〜ねぇよ!」と虚勢を張ってる奴に限ってやられるんですよね〜逆にな〜んも感じなくて鈍感タイプって不思議と何ともないんですよ。人間界のいじめと一緒で、絡んで反応するほうがあっちもやり甲斐がある。全くの無反応じゃおもしろくないんだと思います。ちなみにメディアの心霊番組などで「いま触られました!」っていうお決まりのリフがあるけど、オッサン的には本当かな?と思う。こちらがあちらに触れられないように、あっちもこちらに手出しが出来ないのでは。酷い動画になると人が引きずられてるけど、とてもオッサンには信じがたい。オッサンの経験から今まで一度も接触は無かった。視覚的・聴覚的にはあったけど触覚は皆無だった。それがたまたまなのか、人によって感覚が違うのかも知れないけど…っと今回は怪しい話から入ったのですが、まぁ、あんなもんは見ないほうがいいし見る必要もないですよ。な〜んも良い事がないし、ここまで読んだ方が感じた通り「んな訳ねぇ〜じゃん!」と一笑に付されるか人格を疑われるかのどちらかだ。というわけで、いくら好きな釣りとは言え夜の出撃なんて信じがたい話だ。あちらさんは24時間営業で昼夜関係ないんだけど、夜は人間側も敏感になるからアンテナの感度が違う。だもんで夜&水辺なんて最悪の相性である。釣りモノってけっこう暗くなった夜に釣れるのが多い。暗くなることで魚の警戒心が薄れ、エサをよく食べるから。なので友人や釣り仲間から「今度、夜に行こうよ!」と誘われたりするんだけど、オッサンは「滅相もございません!結構でございます!!」と丁重にお断りするのが常だった。しかし、何で断らなかったのか記憶がさだかでないが、その夜のアナゴ釣りは断らなかった。単にアナゴが食べたかったのか、興が乗ったのか、もう大丈夫と思いたかったのか…恐怖の夜海に繰り出したのだった。アナゴ釣行に望むにあたり準備をしなければならない。タックルはシロギス用で代用できるらしいから助かるが、仕掛けは独特のものだった。リーダーに発光するケミホタルを取り付け、釣り鐘オモリという見たこともないオモリの下に針が位置する仕掛け。なんじゃこりゃあ〜!(「太陽にほえろ!」ジーパン刑事)だった。この仕掛けで船下に着底させ、小突きまくるという釣り方らしい。シンプルと言えばシンプルで初心者には優しくて入りやすいが、オッサンには甚だ疑問だった。実釣したが、当日は激渋な日だったらしくオッサンの釣果は二匹…その釣果はともかく、船アナゴって釣り上げたアナゴを捌いてくれるサービスがとてもありがたかった。まぁ、あんなクネクネした生物を自分で捌くなんて普通は出来ないだろうし、それ故、誰もアナゴ釣りをしなくなると商売上がったりだろうからお捌きサービスが定着したんだと思う。他の釣りモノでも捌いてくれないかな〜しかしいくら渋い夜だからといって、単にお魚側の原因だけなんだろうか?ず〜っと疑問だったんだけど、どう考えてもそれだけじゃないような気がしてならなかった。釣りの肝はどこまでアタリを拾えるか?が勝負その疑問とはあの仕掛けである。釣り鐘オモリの下に針が配置されるアナゴ仕掛け。どんな釣りモノにも言えるんだけど、オモリの下に針が来るのは小さなアタリが取れないのではないだろうか?コレが天秤とかを介して分岐してればまだ良いけど、オモリの真下に針なんて居食い系のアタリには全く反応できないだろう。何であんな仕掛けが定着してるの?誰も疑問に思わないのだろうか?そこで他ではどうなっているのかを調べてみた。しかし全国的にはアナゴ釣りは陸っぱりがメインらしくて、船に乗ってアナゴ釣りをするのは東京湾か宮城県の一部でしか見つからなかった。どこかではスポット的に船釣りもあるんだろうけど、それは分からない。つまりはアナゴの船釣りはあまりにニッチな釣りモノで、それゆえ釣り人口が限られ、進化が止まっているのでは?釣りとはその土地土地のカラーがあって、それらが相互作用や両方向のインタラクションによって進化してゆく。しかし今回のアナゴの船釣りのように一部のスポットでしか行われてないものは、一度そのやり方が定着してしまうとなかなか進化しずらいものだ。そこでオッサンが目を付けたのは、もう一つのスポット宮城の船アナゴ釣りである。こちらの仕掛けは東京湾とは違って、胴付き仕掛けと呼べるもの。コレを見た途端オッサンの頭上のLED電球がペカ〜っと光った。「コレやん!」考えてみれば、オッサンが釣りで使っている仕掛けは胴付き系が多い。オモリを一番下に配置しハリスはその上だから魚のアタリには敏感だし、一番重いオモリが一番下だから操作もしやすい。反面、東京湾の釣り鐘オモリ仕掛けは20号とか25号のオモリの下に針が来るもんだから、アナゴがかなり引っ張ってあの重いオモリを動かさないとアタリとして感知出来ない仕組み。そんなハッキリしたアタリって全アタリの何割あるん?アナゴのことはよく分からないけど、他の釣りもので考えてせいぜい1〜2割が良いところだろう。つまり少なく見積もっても5倍のアタリを見逃しているということだ。コレじゃ〜2匹しか釣れないのも納得。このオモリを引っ張らないとアタリにならないのはどうにも…コレが船アナゴ釣り胴突き仕掛けだ!っという訳で、忘れないうちに船アナゴ釣りの胴付き仕掛けを作ってみることにした。参考にしたサイトは、ご丁寧に仕掛けの細部まで載せてくれてとてもありがたかった。その仕掛けは船宿のオリジナル仕掛けで、マネして作るのもOKだそうでなんて懐の深い船宿なんだ!?写真では分かりづらいので図にしてみた。図解「コレが船アナゴ胴付き仕掛けだ!」アナゴって釣り上げるとグルグルと仕掛けに巻き付いてくるから、オリジナルはもっとごついラインで作っていたんだけど、オッサンは手持ちのラインで誤魔化した。あくまで見た目だけマネてみただけだから本物とは違うんだけど、形だけはこんな感じ〜で作ってみた。【今回使った材料】ライン:ナイロン7号ヨリモドシ・スナップ付きサルカン:7号くらいオモリ:六宝型20号(オモリは小田原でも何でもお好きなもので!)気分で発光玉では作っていきましょう!まずはナイロン7号2本を撚ってハリスを作ります。先述の通り、アナゴが仕掛けに絡まっても容易に外せるようにゴツく作ります。逆を言えば、仕掛けが繊細じゃなくてもアナゴは喰ってくるということですね。ナイロンラインを1mカットし、ヨリモドシを入れます。頂点にヨリモドシが来るように半分にして、エイトノットで固定。結び目はなるべく小さくこのヨリモドシがハリスの先端部になり、幹糸方向に向かって撚っていきます。次にヨリモドシを固定していよいよ撚り始めます。オッサンはこんな感じに固定。固定方法はど〜でもいい2本のラインを撚りますが、一回一回しっかりと撚らないとほどけてしまいます。力加減が肝で、緩いとほどけるし強すぎると変な形になるし、2本を均等な力で撚らないとコレまたいびつになる。けっこう力加減が難しいぞ!先端より27cmまで撚ったら片方のラインにヨリモドシを入れ、再び撚り始めます。コレを忘れると一本針になっちゃいますよ〜無心で作業してると忘れちゃうんだよね今ヨリモドシを入れた箇所から15cmまで撚ったら、撚ったラインごとエイトノットで固定します。コレでちょうど13cmの長さになるハズ次は幹糸と直接連結します。この直結というのがこの仕掛けの肝らしい。幹糸の然るべき位置に、いま撚ったハリスの一本をエイトノットで仮固定。仮固定すると作業がしやすいその流れでハーフヒッチを5回やって固定。次は反対方向に反対回しのハーフヒッチで5回やって固定。これで完全に固定この直結部から幹糸の下側3cmにスナップ付きサルカンとオモリ。上側60cmにサルカンを付ければ出来上がり!コレで完成じゃ!針はお好きなもので良いと思いますが、5号前後のラインをパイプに通す形が一般的なのかな。でも針は何でも好きで良いと思いますよ!ヨリモドシ部に発光玉を入れてもgood!この仕掛けは太いラインを撚る事によって、ハリスに張りをもたせてアタリを逃さないという事と、アナゴが仕掛けに巻き付いても簡単にほどけるのが武器。アナゴのアタリ方は千差万別で小突いて何かしらの違和感を感じたら即アワセ!&掛けたら一気にリーリングにて巻き上げ!じゃないとアナゴが仕掛けに巻き付いて面倒なことになるらしいです。釣り鐘オモリ仕掛けでは即アワセじゃなくて喰わせるみたいに言われるけど、魚がエサに興味を持って喰い付くのはホンの一瞬。このブログで何度も言ってるように魚にはハリスも針も見えてます。その危険を犯してエサを喰ってくるんだから、二度目のチャンスは無いと思って一発で勝負を決めましょう!この仕掛けは、仕舞いと持ち運びのために巻いてしまうと巻き癖が付いてしまい、せっかくの張りのメリットが活かせません。なのでハリス部は直線にしたまま仕舞いましょう。オッサンはステンレス線のパッケージを使いました中身を出して適宜な長さにカットして保存&このまま持ち運びワイヤーハリスVer.とオモリのいたずらついでなのでワイヤーハリスVer.も作ってみた。この胴付き仕掛けは、ハリスをピンと張ることにより小さなアタリを逃さないというのが売り。なのでハリスが常に安定した一直線になるワイヤーを使えばいいんじゃね?と思った次第であります。「撚ることもないから手間も省けるし!」といういやらしい魂胆が無いわけではない。コレがワイヤーハリスVer.だけど、写真じゃ分からんがな幹糸とハリスの結線部及びハリスと上針部にはクロススイベルを使用。左側のクロススイベルを使用幹糸とハリスの結線部。さすがにココは直結できん!上針とハリスはクロススイベルを通してガン玉で動かないように下針部のヨリモドシとの結線はスリーブを使って固定スリーブをペンチでしっかり潰して固定このワイヤーVer.は簡単にできて直進安定性があり、仕舞いも運びも丸めて大丈夫だから面倒くさくない。デメリットはワイヤーはステンレス製で重量があり、ナイロンVer.のように海底でフワリではなくドスン!と沈んでしまうので、アナゴがそれをどう思うかが謎。予想ではナイロンVer.に比べてアタリの感度は鈍くなるかな…まぁ、ナイロンVer.の予備としての位置づけ。アナゴという生物は光るものに反応するらしいので、オモリにも小細工をしてみました。オッサンの手持ちに高輝度の蓄光テープがあったので、オモリにベタベタと貼り付けてみた。コレを加工していろんなアイテムに貼り付けてる六宝型のオモリに貼り付けた暗いとこんな感じにボヤ〜っと怪しく光る最近ではケミホタルをハメ込めるオモリがあったりして、その派手さキラキラ感は増すばかり。アナゴは光りに反応するらしいので、そんなキラキラが好きなら夜行性じゃなくて昼間に活動すればいいのに…とも思うがそれは嫌なんだろう。なんて面倒くさい生き物なんだ!?今回はオッサンの素朴な疑問に応えるべくアナゴ仕掛けを自作してみたんだけど、どうやら考えることは皆同じらしい。例の釣り鐘式オモリにもハリスをオモリに中通しにする誘導タイプがあったり、天秤を使うにしてもオモリの重さがアタリに干渉しないように工夫してあるタイプも出てきた。やはりアタリに対してあの重さがネックになるという現実は皆が感じるところ。別に従来の釣り鐘式を否定してるわけではなくて、場合によってはその方が有効なシチュエーションも多々あると思います。アナゴ釣り初心者のオッサンなんぞにエラそうに言われる筋合いは無い!と怒られそうですが、下手には下手なりの戦い方があるのです。そのひとつが今回の胴突き仕掛けであり、それを証明すべく実釣すべきですが、アナゴ釣りの予定は全くの未定。早く行きたい気持ちは富士山よりも高い山々なのですが、如何せん夜の船出はためらわれる。万が一、行く事になったら”耳なし芳一”みたいに全身に経文を書いて出撃しようと思ってます。もちろん耳にも忘れずに!
完熟おやじの充実生活
「 東京湾 」の検索結果
-
-
ホットなタチウオマダコリレー船のハズだったが…2019年8月3日。タチウオ&マダコのリレー船に乗ってきました。釣り場:マダコ-大師沖&本牧沖 タチウオ-観音崎沖天気:晴れ釣行時間:8時00分(潮位:184cm下げ二分)〜15時30分くらい(潮位:75cm上げ三分)中潮釣果:マダコ2匹(0.8kg&0.5kg)タチウオ6匹(60cm〜90cm) タコ釣りロッド:アブガルシア-タコスフィールド TKFC-692MH-BS リール:アブガルシア-シルバーマックス ライン:PE6号 オモリ:自作スチール棒オモリ(25号相当)ルアー:自作デビルパラシュートもどき【生餌Ver.&デビルクローVer.】生餌:豆アジデビルクロー:パールチャートペッパー&ホワイトラメタチウオ釣りロッド:ベイゲームXタチウオ82 195MHリール:フォースマスター400(電動両軸リール)ライン:PE1.0号(↑全てオッサン2号からのレンタル) 天秤:オッサン自作のタチウオ片天秤オモリ:80号 仕掛け:ハリス7号&ワイヤー タチウオバリ1/0号 全長2mの一本バリエサ:コノシロの切り身沖釣り専の友人オッサン2号の会社の釣り部では、年に数回船を仕立てて沖釣りに繰り出す。オッサンはその会社には縁もゆかりも全く無いんだけど、釣り部長の2号の友人枠で参加することがある。いつもはアジとかシロギス釣りとかの釣りに熱心ではない部員でも釣れないことはない獲物なんだけど、今回はタチウオ&マダコという初心者は厳しいんじゃね?と思わせる獲物である。どちらの釣りもそれなりのテクニックと体力が要求されるし、酷暑の炎天下である。糞暑い中、全然釣れない船内にはグデングデンの空気が立ち込める…もう既に企画倒れの予感しかしない。かく言うオッサンも、タチウオ釣りは今回で2回めだし、タコ釣りも川崎新堤での2回だけで船に乗っての釣行は今回が初めてである。しかし、前回のタチウオはよく釣れて良い印象を持ってるし、マダコは今年は当たり年なので釣れまくってるから楽しい。なので、オッサン的にはド真ん中ストライクの釣りものコンビである。2号もオッサンの好みは心得ていて、今回の企画はすぐに誘いを入れてきた。2号がこの企画を持ち込んだ時は、小鼻が膨らむのを抑えながら「まぁ、考えておきますわ!」と返事したが、人が”考えておく”と言う時はOKという意味である。仕掛けがフォールするやいなや(=as soon as)バクッ!っと喰らいついて釣り上げられたくらい単純に釣られたオッサン。オッサン2号もさぞほくそ笑んだことだろう。当日の天気は予報通りのピーカン。雨は困るが、せめて薄曇り程度で勘弁して欲しかったが、悲しいくらいに快晴で溶けるくらいに暑い。朝6時過ぎにオッサンの自宅を出発したが、もうこの時間で既に暑い。向かう船宿は東京大田区南六郷の「ミナミ釣船」さん。オッサンの地元なんだけど、乗るのは今回が初めての船宿。まぁ、オッサンはあまり沖釣りやらないから、どの船宿も初めてばかりなんだけどサ!受付を済ませ船に乗り込んで準備を始める。このミナミ釣船さんの船着き場は、多摩川最下流に面してる【六郷水門】の中という、珍しくも出し入れが大変そうな場所にある。六郷水門は昭和6年に作られ、付帯する現役最古の排水機場のひとつである「六郷配水機場」と共に治水に役立ってきたらしい。確かにレンガ張りの古めかしい作りになっていて、歴史を感じさせる。オッサンも数年前はこの水門までテナガエビ釣りに来てたこともあったが、2017年に関東を直撃した超大型台風21号の影響で大量の土砂がたまってしまい、ご機嫌なテナガエビ釣りが難しくなってしまいました。残念ながら、それ以来はここでテナガエビ釣りをやってません。まぁそんなエキセントリックな場所にあるので、潮位によっては水門内へ船の出入りができない事もあって、その場合は小舟に乗って多摩川沖に停泊している本船に乗り換えたりするそうな。幸い当日は水門内の船着き場からの河岸払い(船出)だったんだけど、帰港の時間帯は潮位が低く時間調整になるかも…と船長が言っていた。2号は今回の企画の幹事なので早目に到着するが、なにせコヤツの荷物が多いのなんの…メンバーに配る仕掛けやら、貸し出すタックルやら、獲物を入れる大型のクーラーボックスやら(釣り後は釣れた獲物を肴に宴会が予定されてる)、尋常でない量なのである。2号は今日もまともに釣りなんてできないだろうに、幹事も大変だなぁ〜と他人事のオッサンだが、タチウオのタックルを借りる身分なのでちょっとはお手伝いをしておく。乗り込む船は少々くたびれてるが、大型船なので広くて快適だ!船が広いといいね〜!本日の潮周は中潮なんだけど、大潮明けの翌日だから潮の流れは早い。この時期でもタチウオ釣りは水深60m以上を狙うので、潮流が早いと厳しくなる。なので、まず初めにタコ釣りをやりながらタチウオポイントである観音崎沖に向かって移動しつつ、干潮の潮流が緩くなる時間帯を見計らってタチウオを狙う作戦。タコ釣りはまず多摩川河口の大師沖からやるらしいので、出発したらすぐのポイントになる。という訳で、本日の生餌である豆アジをあらかじめ解凍しておく。猛暑だからすぐに解凍できるだろうて…メンバー全員揃ったので、船長が餌の付け方やら釣り方のレクチャーが始まる。んが、タコ釣りはテンヤ仕掛けの説明なので自作デビパラを使うオッサンには関係ないし、そもそもロクに人の話を聞かないタチなので、レクチャーを他所にせっせと自分の仕掛けの準備を始める協調性のないオッサン。せっかくの説明なんだけど、全く聞いちゃ〜いないオッサンまずは、これまた自作のエギ天秤を使って生餌Ver.とデビルクローVer.のダブルで攻める作戦。コソコソと自分勝手に準備を進める今回は豆アジを使うのでエサの重量があるから浮くかどうか心配だったんだけど、実験したらちゃんとアジが浮いたのでホッとする。いよいよ出発。六郷水門をギリギリでくぐり抜け、大海原へレッツ・ブ〜!!趣ある六郷水門をくぐり抜け発進!ふと見ると、2号がまたしても妙なことになっていた。日焼け止めのマスクを被るさまさらにダブダブな暑苦しそうなジャケットを着ていて、暑くないのか?訪ねたら、これは近頃流行りの扇風機付きの空調服らしい。確かに、仕事の現場でよく見るようになったが空調服を着てる奴って、ろくすっぽ作業しない現場監督系が多い気がする。でも昨年あたりからは、スタイリッシュで作業しやすい空調服が出回ってるから、装着してる職人も多くなってきたな。まぁ、オッサンは着たことないからよく分からんけどサ。見た目は暑苦しそうだが涼しいらしい多摩川の最下流は、現在、川崎浮島と羽田空港を結ぶ橋を作ってる。まだ橋脚も完成してないけど、こんなんで来年のオリンピックに間に合うのかな?まぁ、突貫工事で間に合わせるんだろうな…まだこんな程度だけど、間に合うんか?爆釣のタコ釣りのハズが…多摩川を出たな〜って思ってたら、すぐに船が減速し始めた。どうやらもうタコポイントに到着したらしい。目の前には、東京アクアラインの川崎側の入り口の浮島換気口が見える。いきなり、こんなところでタコ釣りするんだ!余談だが、この換気施設は最初はピラミッド型をしてたんだけど、羽田空港D滑走路供用開始に伴い、換気口上部が航路の障害となったので上部12 mを取り払う改修工事が行われたらしい。という訳で現在は不自然な台形になってしまい格好悪いんだけど、この改修工事費用は行政サイドが出したのか、羽田空港サイドで出したのか気になるところである。話をタコ釣りに戻す。自作のタコエギ天秤にデビパラのデビルクローVer.と生餌Ver.のフルオプションでスタートダッシュをかける作戦。オッサンのロッドは船タコ釣り用だから、遂にその実力を発揮する時が来た!頼むぞ!タコスフィールド!!期待を込めて第一投を投げるが、着水するとすぐにラインが緩む…アレ?浅すぎない?オッサンの釣座はミヨシ(船の一番先頭)なので陸が近いのだが、あまりにもキワを攻めすぎたようだ。一度回収し、もっと深いであろうポイントに投げる。それでも水深は4〜5m程度で浅いな…まぁ、タコさえいれば喰ってくるだろうて。優しく丁寧に小突き始めるが、陸っぱりの釣りと違って船は流すので、当たり前なんだけど自分の立ち位置が移動する。オッサンが船釣りに慣れてないからなんだけど、そんな塩梅ですこぶる釣りがやりにくい。船の後方では早速タコが上がっているようで、そっち方面から歓声が上がっているが、オッサンとこには何も変化もなく静かなものである。しばらくやり続けるが、な〜んかやりにくくて、誘いもアタリも取れないというか、そもそも底が取れてないんじゃね?本日は潮流も早いので、デビルパラシュートという仕掛け的には苦手な潮加減だと思う。タコが釣れなくて焦っているので小突きも早くなったりして、気づけば底からデビパラが浮いていて、余計にタコが喰ってこない悪循環。船中、大漁ではないがほぼ全員がタコをゲットしたご様子だが、オッサンにはタコの気配すらない…デビパエラを生餌Ver.とかツインVer.とかいろいろやってるんだけど状況は改善せず…タコ釣りが一段落し、大師沖から横浜方面に移動するようだが、途中、川崎新堤の側を通りかかる。「もうタチウオやらなくていいから、俺だけ川崎新堤で下ろしてくれ〜!マジで!?」と心底思った。すぐソコの川崎新堤で下ろしてくれ〜!オッサンの心の叫びも虚しく川崎新堤を通り過ぎる。次のタコポイントはつい最近ここだけで数10匹も釣り上げたというポイントらしい。ここでもポツリポツリ程度だけどタコは上がるが、相変わらずオッサンには音沙汰なし…タコは大量にいると思うんだけど、全くアタリがないというのはどういう事?船中全く釣れてないわけじゃないから、オッサンだけ根本的に何かがおかしいんだろうと思うが、何がおかしいのかさっぱり分からず。とっかえひっかえ仕掛けを変えてみるが、何も変わらないんだよな〜いろいろやってるんだけどね〜…そして、やっとタコのアタリがやってくる。これは根掛りではなく間違いなくタコが乗った感触だ!コレを逃したらタコボウズ確定間違いなしだったので、いつもよりも長めに小刻みにシェイクしてタコをしっかりと乗せる。そしておもむろに大きくアワセると、乗ったぁ!その重量感から良型だ!水面にタコが見えると、やはり良型がくっついている。中乗りさんがタモ(網)ですくってくれて無事ゲット!0.8kgくらいの食べごろサイズだった。やっとタコ釣れたよ〜!一匹釣れて、これから爆釣開始じゃ!と気分あらたに頑張ってみるが、またしても音沙汰なし…ど〜なっとんじゃ!この海ぁ〜!!もしここにダイナマイトがあったら、ダイナマイト釣法で一瞬でカタをつけちゃる!くらいにこの海が憎い。2号がチョロチョロと来ては「釣れた〜?」とオッサンの不機嫌の火に油を注いでくれる。「船に乗ってコレは無いんじゃね!?もっと釣れるポイント行こうよ!」と不満をぶつけるが、「まぁ、こんな日もあるさ!」とオッサンの不満をスルリと流す2号。あまりにタコが釣れないから半分ふてくされモードのオッサン。集中力も全くなくてヒマだから、隣で初心者に偉そうにレクチャーしていた2号の空調服の扇風機の目の前に豆アジを晒してやった。空調服って、吸い込んだ空気は首周りから排出される構造になっている。魚の臭いが服の中に充満し、そのニオイは首周りから鼻にアタック!をイメージしてたんだけど、アジがイマイチ臭わないのか、コヤツが鈍すぎるのか全く反応を示さない2号。無反応でつまらないから、釣れないタコ釣りに輪をかけてつまらなくなるオッサン。結局、もう一匹釣り上げてタコ釣りは終了。船中そこそこ釣れたらしく、失敗ばかりの釣り企画が今回は成功で機嫌が良い2号。コヤツとは裏腹に釣れなくて不機嫌なオッサン。きっと釣れない原因はあるんだろうけど、もうその原因を考えるのもかったるいので何も考えないようにした。「きっと今日はオッサンの日ではないんだろう…」そして「この後のタチウオ釣りもダメだろう…」と思うことにした。オッサンはネガティブ人間なので、期待さえしなければダメだった時のダメージを軽減できる。後ろ向きで前向きなセルフ・ディフェンス法である。タチウオで挽回のハズが…憎っくきタコ釣りが終わり、次のタチウオ釣りの現場、観音崎沖まで爆走するが、到着するまで時間があるからノンビリとタチウオ釣りの準備にかかる。タックルは2号からのレンタルだが、シマノのベイゲームXシリーズのタチウオ専用ロッドと小型両軸電動リール「フォースマスター400」という豪華な布陣。2号はシマノ派なのでこのようなタックルになるが、レンタルには必要十分過ぎるレベルのタックルである。確か昨年も同じタックルを借りた気がする仕掛けはオッサン自作のチドリ天秤とハリスは先端20cmをワイヤー仕様の危険な奴。実は近所の釣り好きな友人から、「ワイヤーハリスはオマツリした時にPEラインをぶった斬る事があるから、禁止されてる船宿も多い」というのを聞いた。しかし、コレを聞いたのは釣り当日の朝という今更そんな事言われたって…という時だったので、どうにもならず。まぁ、今日は仕立船だから、その時は笑って誤魔化すしかない訳でして…オマツリ時には凶器となるワイヤーハリス驚きは使用するオモリが80号という、この時期にしては重量級で、それだけ潮流が早いということだがこの重さをシャクリまくるというのも骨が折れそうだ。このオモリでシャクるのか…ロッドの準備ができたのでお次はエサの仕込み。昨年同様に、怪しい粉を振りかけてタチウオをアッパラパーにして釣り上げる…というネタは昨年もやったと思いますが、今年もそんな感じです。市販の摂餌促進剤をエサに振りかけるが、これも昨年の余りの一品ですが、はたして賞味期限は大丈夫なのか?怪しい粉を振りかけまして…しばらく置いてから、エサ付けの練習をば。なにせタチウオ釣りは一年ぶりなもんで、エサ付けすらすっかり忘れてる。エサのコノシロが回転しないように両端をハサミで水平にカットし、センターにハリを通すように丁寧に。こんな感じかな…程なく、タチウオ釣り現場の観音崎沖に到着するが、相変わらずの大船団である。こんな広い東京湾でも、タチウオが釣れるご機嫌なポイントは数カ所くらいしかないらしい。すげぇ密集地帯「始めてください。水深75mで70m〜30mで反応あります!」とのアナウンス。エラい幅が広いな…シャクるのも大変だなぁ〜と早くも気が滅入るオッサンだが、気を取り直してタチウオ釣りスタート!スルスルと仕掛けが落ちてゆくが、今のところ潮の速さは感じられず。とりあえずは指示通り70mまで落としてから、シャクリ始める。まずは基本の45°から水平までシャクり、リールを半回転巻く。最初はぎこちなかったけど、一度経験しているので何となくリズム良くシャクれるようになる。気をつけるべきポイントは、上までシャクったら一旦しっかりと止める事。小魚がピッ!ピッ!って泳いでいるイメージでエサを踊らせる。すると、水深55mでいきなり根掛りみたいにズドン!と止まる。来た〜!!っと大きくアワセると乗ったぁ!電動リールのスイッチオン!ウィ〜ンと自動的に巻き上がる。電動って楽ちんでいいね〜!時おりタチウオが強く引き込むので、リールの巻き上げ速度を調節しつつ確実に上げる。昨年はこんなやり取りする余裕がなかったけど、今年は余裕って感じだね!上がってきのは指三本くらいのこの時期のスタンダードサイズ。一投目で上がってきて気分良いオッサン。もちろん船中の第一号素早くエサを付け替え、次はアタった水深55mプラス2mまで落としてシャクリ開始。すぐにアタってくるがハリ掛かりせず。粘ってみるが喰って来ないので一度回収し、エサつけ→投入すると次は掛かった!上げてると結構重くて、何度も引き込むのでリールの速度調整も楽しかった。二匹目は本日の最大サイズの指4本クラス。まぁ、指4本という事でこの時合いを逃さないよう素早く投入し、スタートダッシュをかけるオッサン。開始30分で4匹上げて気分良いが、アタリが遠のいてくる…すぐにシャクリのリズムを小刻みに修正。数10cmシャクって1/4回転で小さく早めの夏タチウオ仕様に変えると、小さくアタってくるが本アタリして来ない。それでもリズムを変えずにシャクリ続けるが、なかなか引き込まず…最初のアタリから30mシャクリ続けてやっと大きく引き込んだ!上がってきたタチウオはハリまでゴックン飲み込んでいて、ワイヤーハリスじゃなければ切られていただろう状況だった。このタチウオを最後にアタリが遠のいた…船中メンバーもタチウオ釣りに慣れた頃、人のお世話で忙しかった2号が帰ってきて、やっと一投だけタチウオ釣りをした。やはり竿頭をとるだけあってシャクリが上手い!その一投でタチウオを釣り上げながら「こうやるんだよ!タチウオ釣りなんて簡単じゃん!!」と豪語していたが、確かに言うだけの事はあるよ君ぃ!この時はオッサンのシャクリと2号のシャクリのリズムが同調していて、オッサンのシャクリが間違っていないことを確信した。しかし状況は悪くなる一方で、潮流が早すぎて80号のオモリすら大きく流され始めた。何とかもう一匹上げたんだけど、このタチウオがラスト。釣り続行不可能となり、タチウオ釣りは90分ほどで終了。何とも煮え切らないタチウオ釣りとなったのでした。船中、各人0〜1匹と厳しい中、スタートダッシュを決めたオッサンは6匹と竿頭だけど、たった6匹で頭って言ってもね〜この後の宴会用のタチウオも寂しい状況だが、宴会に参加しないオッサンはその貴重な6匹をお持ち帰りするというKYぶり。しかし、オッサンだって大枚はたいてるんだから当然の権利で断固として持ち帰ったのでした。オッサンは全然ダメだったけど、タコはぎょうさん釣れたからいいじゃん!と思ったけど、タコは下ごしらえに手間がかかるから宴会を開催するその店では持ち込み禁止らしい。タコはともかく、タチウオがここまで釣れなかったというのは2号も計算外だったようである。まぁ2号のリサーチが甘いと言わざるを得ないが、こんな塩梅でコヤツが出世するのかどうかは甚だ疑問だが、その会社に全く関係ないオッサンとしては「とりあえず頑張れ!」としか言えないのである。六郷水門の中に入れる潮位まで多少の時間調整をして帰港。帰ってきたよ六郷水門タチウオは釣り始めのあの調子なら確実にツ抜け(10匹)すると思ったんだけど、状況が悪い方に転がって残念でした。でもオッサン的にはタチウオ釣りは性に合っているのカモしれません。次はいつになるのか分かりませんが、好印象の釣りものであることに変わりないが、問題はロッドとリールが無いという事でして…やはり、やるなら電動の方向なんですが自分で買う気も身銭も微塵もないから「今後とも2号さんよろしくね!」という事でひとつ。しかし、納得できないのがタコ釣りだよな〜なんで釣れなかったんだろう?実は答えは分かってるんだけど、あまりにもトホホな原因だからここで発表するのも何だし…果たして、オッサンは今後船でタコ釣りするのか分かりませんが、その時は修正できると思います。しっかし暑かったぁ!!いくら沖合でも暑いもんは暑いぞ!冬も厳しいけど真夏も負けじと厳しい沖釣り。やはり船釣りするなら、秋とか春が爽やかで良いな〜