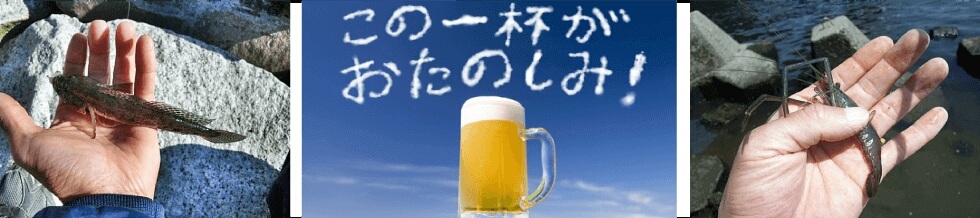2022�N�Q��ڂ̑�����e�i�K�G�r�ނ�͂���Ƃ��I
2022�N�S��29��
2022�N�Q��ڂ̃e�i�K�G�r�ނ�ɍs���Ă��܂����B
�|�C���g�F������Βn�̑Ί݁i��葤�j
�V�C�F�܂�
�ލs���ԁF6��30���i����145���������R���j�`8��00���i����91���������U���j�咪
�����F19��
�މʁF�R�C�@

�ƁF2.1���i�ʕ�U�ƍs�_�����̍��̊Ɓj��2.1���i�V���c�P�u����v�j�@
�����F�t�����J�[�{��1.5���@�n���X�F�i�C����0.3��
�n���F�^�i�S-�ɏ��V�����@�E�L�F�ʃE�L-�W���^���V���@
�I�����F�K����-�a�@�G�T�F�~�~�Y
�d�|���F�n���X�Rcm�̎}�X����{�j
�{������S�[���f���E�B�[�N���n�܂�܂����B
���N��GW�͂��������̐l�o���\�z����Ă��āA�ό��ƊE�������������n�߂��Ƃ��낾�낤���A���̂ɂ����͋C�����������̂ł���B
�I�b�T�����x�݂ł͂��邪�A�J�����_�[�ʂ�Ԏ��̓��������x�݂��B
�u�P���I���Ԃ���`10�A�x�Ȃ�Č����Ă�̂ɁA��ѐ̋x�݂Ȃx�݂̂����ɓ��邩!?�v
�u�ǁ`���A�A�x���̕����Ȃ�Ďd���̈˗��������ˁ`�����!?�v
�܂��A�s�������������̗��Ƃ̉^�c�Ȃ͂���Ȓ��x�ł���B
�����������獡�N��GW�͗\�肪�������B
���{�O���Ղɐ��������z�K�̌䒌���ɍs���\�肾�����B
���͍Ȃ̓c�ɂ��z�K�ŁA�䒌�Ղ��J�Â���n�悾������A�䒌�N�͖���K��Ă����B
�����m�̒ʂ�A�䒌�Ղ͓ДN�Ɛ\�N���Ƃɍs���Ă��āA�Y������n��͂��̏������^�c���ő�ςȂ��Ղ�ƂȂ�B
�z�K�_�Ђ͏�ЂƉ��Ђɕ�����Ă��āA����ɂ͑O�{�{�{�i���Ђ͏t�{�H�{�j�Ƃ���A�����ւS�{���̌䒌�����Ă�B
�܂��ЂW�{���ЂW�{�A���v16�{�̌䒌������A������V�N�ڂ��ƂɌ��đւ���̂ł���B
�Ȃ̓c�ɂ͏�Ђ̕��ŁA�I�b�T������������O�̕t�������Ă������疈��s���Ă�����A����łS��ڂ̃n�Y�������B
�������A����͗�̃E�B���X�����ŁA�W�҂��u���������A�ǂ�����̂��c�v���Ȃ�_�o���g�����炵���B
�����䒌�Ղ̗��j�ň�x�������~�������Ƃ��������炵���A���̔N�͑�Q�[�ƂȂ�u���̐_���͂��Ȃ˂Ȃ�Ȃ��I�v�Ƃ����|���o���オ�����炵���B
���~�Ƃ��I�����͂Ȃ����A�l���W�߂鎖���o���Ȃ��̂ł͌䒌�Ղ����藧���Ȃ���펖�ԁB
�͂����āc�c
���ꂩ��䒌�̑�܂��Șb�����܂����A�����܂ŏ�Ђ̘b�Ȃ̂ŁA���Ђ̕��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂�������܂���B�������炸�B
�䒌�Ղ̍H���͑傫���u�R�o���v�Ɓu���g���v�ɕ�����A�R�o���͐�o�����䒌���A�R���珊��̏ꏊ�ւ��̒��̒S���n��̎��q�B���l�͂ň�������ړ�������B
���Ȃ݂Ɍ䒌�͎���150�N�ȏ�̃��~�m�L����Ȃ��ǁA�̂͒n���̎R�����o�������ǁA���݂͂��̂悤�Ȗ͖����炵���A���������o���ĉ^��ł���炵���B
���̌䒌�ɂ��̂����������҂ݍ��m��i�e�j�ƌĂ��j����A���ꂼ��ɍׂ��j�i�q�j�j�����āA�l�͂����ň�������̂ł���B
�d�ʂ�����10�g���قǂ���䒌�����ł͂Ȃ��A���̒��ɃL�c�L�c�Ől��������������S�̂̏d�ʂ͂��Ƃ̂ق����B
��Ђ̌䒌�ɂ́A���ؖ{�̂Ɂu�߂ǂł��v�ƌĂ��q�����߂ɓ�{���O��Ɏ��t���A�\�R�ւ����q���������B
�����ڂ̓i���N�W�̃c�m���O��ɂ��銴���Ȃ��ǁA�o�����X�������Ȃ邩��ړ�����ɂ��Ă���ς��B
���R�ԗւȂ�ĕt���ĂȂ��āA���������Y���Y���������邩��A�ЂƂ̒��̈ړ��ɂ͉���l�̐l�o���K�v�ɂȂ�A�u�l�����������z�K�䒌�v�Ƃ������t�����邭�炢�̐l���J��o���B
�䒌�͊e�n��̎��q�����G��Ȃ��̂ŁA�䒌�Ƃ��Ȃ�Ƃ������o�ł���B
���Ȃ݂Ɉ�������̂͘V��j���W�Ȃ����ǁA�䒌�ɏ���̂͒j�������ł���B
�W�{�̒����������������S���Ԋu���炢�Ɉ�����Ă䂭���ǁA�O�̒��������Ĕ����Ă͂����Ȃ��Ƃ����|������B
�䒌�ɂ͊K���������āA�ォ�珇�Ɂu�{�ꁨ�O�ꁨ�{�O�{�O���O�O���{�l���O�l�v�ƂȂ��Ă���B
���̏��Ԃ́A�e���̑呍��ƌ�����ō��ӔC�ҒB�������ɂ��������������Č��肳���̂ŁA�呍��͐ӔC�d�傾�I
�Ȃ̂ŁA�O���̒���ǂ������Ȃ�ĉ�����ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B
���Ă������A�c�ɂ̋������H�ʼn���l�����������邠�̋������Ȃ�ĕ����I�ɖ���������I
�䒌�Վ��́A�g���m�荇���W�Ȃ��N�����Ă����Ƃ��y�����^�_�ŐU�镑���̂����������ŁA���Ɍ䒌���ʂ�䒌���̉����̉Ƃ́A��ςȑ����ɂȂ�B
�䒌�͈��X�s�[�h�œ����̂ł͂Ȃ��A�r���ɋx�e�����邵�A�n���n��̒��Ƃ��Ȃ�A���̒n��̊Ԃł͂��낢��ȃT�[�r�X�����̂łȂ��Ȃ��i�܂Ȃ��B
�䒌���������̖ڂ̑O�Ŏ~�܂�Ƃ��Ȃ�A���̎��q�����������Ĉ���H�����肷�������A���̐ڑ҂ő�Z�����I
�u����H��������Ȃ��I�v�Ȃ�Ď��ԂɂȂ������ɂ�`�A�u���̉Ƃ͂���Ƃ��p���������I�v���Ɠc�ɓ��L�̃��[���A�̊i�D�̃^�[�Q�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B
���Ƃ����āA�䒌���X�`���ƈ�C�ɑf�ʂ肵�čs���Ă��܂��A������������������ʂ̐H�ނ����ʂɂȂ��Ă��܂��B
������ւ��̉^�Ƃ������A������Ȃ̂ł���B
�S�Ă͌䒌����Ȃ̂ł���B
�悭���f�B�A�ʼnf���������͉̂��Ђ̕��ŁA�}�s�ȎΖʂɌ䒌�����藎�Ƃ��u�ؗ����v�ƌĂ��f���B
�䒌�̋��؏�ɑ吨�̎��q���������A��C�ɋ��𗎂Ƃ�����ƂĂ��댯�ł���B
��Ђɂ��ؗ����͂��邯�ǁA��������@���ɃL���C�Ȏp���Ŋ��艺�낷�̂����e�[�}�ɂȂ�B
�Ȃɂ��h�߂ǂł��h���t���Ă邩��A���Ђ݂����Ɉ�C�ɗ��Ƃ��Ή���l�ǂ��납���l��������O�ɏo�邾�낤�ˁB
�ؗ����̑��ɐ��n���Č䒌�𐴂߂�u��z���v��������ǁA���͂��̐�z���̕����댯�B
���́u��z���v�܂ł��R�o���̍H���ŁA�R�����S���̏��{�Ȃ����琅���₽���̂Ȃ�́B
�l���ڂ����܂ܐ��̒��ɓ����Ă䂭���ǁA�X���[�Y�ɐi�߂܂������A������Ƃł���Ԏ��A����Ă��鎁�q�B�͗␅�ɎN����邵�A����Ă���ʒu���������`�����ɒu������ɂȂ�B
�{�����ǂ����m��Ȃ����A�s�^�ɂ������ꂽ���q���~�����镔�����������ɔz�u����Ă���炵���B
�����̊댯�����̂Ƃ������䒌�ɂ����݂��l�́A�m���Ɋ�ՂƌĂ��ɑ��������l���ł���B
���N�A����l�͓��R�Ȃ��玀�l���o�邱�Ƃ�����B
���R�A�����́h���́h�͐��Ԃ��畚�����Ă��Đ_���ł̃^�u�[�ƂȂ��Ă���B
�u�Ȃ�ŁA����Ȋ댯�Ȏ������ɂ��낤�c�v
���ʂ̊��o�Ȃ炻���v�����낤���A���q�B�ɂƂ��Ă̓\�����_��ł���A����Ȋ댯�Ȓ��A�Ō�܂Ō䒌�ɏ���Ă���ꂽ���Ƃ͖���܂Ō�荐�����q�[���[�Ȃ̂ł���B
�R�o���̌�́AGW�ɍs���闢�g���ł���B
������͂����S�[���̐z�K��Ђ��ڂ̑O�ł���A�Ō�̃O�����h�t�B�i�[���ł���䒌�����Ă�u���䒌�v�����ǂ���B
�P�Ɍ��Ă�Ƃ͌����A����17�����a�P�����̋��ł���B
�X�ɂ͌��ĂĂ�Ԃɂ��l�͏���Ă���̂��I
���Ă�ꏊ�����������L�����n�Ȃ�Ƃ������A�����e�ɂ͐_�Ђ̌���������������Ă��āA�n�ʂ͕��R�ł��Ȃ��B
����Ȓ����܂�����l�͂����Ő����Ɍ��ĂĂ䂭�̂��B
����ł����N�p����Ă�����Ƃ͂��Ȃꂽ���̂ŁA���Ɍ��ĂĂ䂭�l�͑f���炵�����̂ł���B
�䒌�Ղ�������s���Ă���̂��͒肩�łȂ��A���̋N����1,200�N�ȏ�O����Ƃ������Ă��܂��B
���\�L�̃R���i�Ђ̒��u��ɒ��~�ɂ͏o���Ȃ����A��̂ǂ�����Ď���s���̂��c�v
�W�҂̕��X�̂��̐S�J�����͕M��ɐs����������Ǝv���܂��B
���̓������A����̃g���[���[�ʼn^�ԂƂ�����a�̑I���������̂��Ǝv���܂��B
�������������Ȃ��͂�������܂���B
�_�l�̒����@�B���g���ĉ^�ԂƂ����̂́A����������ƌ�荐�����鎖�Ԃ��Ǝv���܂��B
�������A�R��������̗���ȂƎv���܂��B
�n��������Ō䒌���ړ������鎖�̂ł���l�o���m�ۂ���̂�����ɂȂ��Ă���ƕ����܂��B
���݂ł́A�䒌�̈ړ��X�P�W���[���͖Ȗ��ɋK�肳��A��������炵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�l���ꂼ��ɓs��������A���߂�ꂽ�������ł����Q���ł��Ȃ������命���ł��B
�����̉Ƃł��A�������Ȃ����ĂȂ��͊��ɉߋ��̃��m�B
������S���I�ɗL���Ȑ_���Ƃ͌����A�n���ł͕s�Q����I�Ԑl�����Ȃ��Ȃ��悤�ł��B
�䒌��ۊǂ��Ă����ꏊ�ł��A24���Ԃ̌������t���Ă��Ȃ��ƁA�_�̒��ɃC�^�Y������邱�̂������B
�`�����镶���̌p���́A�W�҂̑���ȓw�͂ƌ��g�������Ă������藧���́B
���ꂪ1,200�N�ȏ�̗��j�����䒌�Ղł������A�\���Ȃ����Ă͈�u�œr�₦�Ă��܂��Ǝv���܂��B
�ꉞ�A�Ȃ̓c�ɂ̉Ƃ͑呍������߂����Ƃ�����n���̖��m�B
����A�n���̃n�b�s�𒅍���Łh�Ȃ���Ď��q�h�Ƃ��Č䒌�����������Ă���I�b�T���B
�u���߁`�͌��˂��炾����ǁA�ǂ��̉Ƃ̂��H�v�i���z�K�Ȃ܂�j
����������邽�тɖ��Ăȓ����قŁu���`�A�����i�Ȃ̓c�ɂ̉Ƃ̖��O�j�̂���ł��I�v�Ɖ�����I�b�T���B
�u�ف`���I�����`�������ȁI�v
�Ղ̈Ђ���n���X�^�[�ȃI�b�T���B
����Ȗ��m�̉Ƃ̌��ւɂ́A�呍��߂����̒��a�P�����̖{��䒌�̐�g�ƁA�h�߂ǂł��i�Ƃ͌��������T�����炢�̑������j�h���܂邲�ƈ�{���Ċ|���Ă���B
���������m�I
�V�C���������̂ŒZ������ɂ�
����Ȗ�ŁA����̌䒌�Ղ͎c�O�Ȃ���s�Q���ƂȂ�܂����B
�ƂȂ�Ǝ���͂V�N��Ȃ̂ŁA�����Ă邩�ȁ`���H
����̓��C�h�̓y�Y�Ƃ��ĎQ���������������ǁA�c�O�������ȁ`
�܂��A�{���Ɏc�O�Ȃ͓̂c�ɂ�n���̕��B���낤�B
����Ȏ��Ɍ����Ĉ�Ԃ����́h�{��h�������Ă�����āA���G�ȐS�����낤�ȁc
���Ƃ����킯�ŁA���N��GW�͗\�肪�Ȃ��Ȃ����B
���������s���������Ȃ�����A��������I���C�n�ɂł��s�����Ⴈ�����ȁ`�I�I���Ƃ������͑S�������A����ȋ��������͂��Ȃ�������v�������Ƃ͂ЂƂ��B
������Ńe�i�K�G�r�ނ肾�I���āA���N����Ȃ���������I���Ċ����ł����ˁB
�O��̃e�i�K�G�r�ނ肩��͂�Q�T�Ԃقǂ��o�߁B
�{�E�Y���o�債�Ă������̂́A���ۂɋ�炤�Ɖ��������ƎR�̔@���B
�����Ƀ��x���W����I�Ɠ��u��R�₵�Ă������A�V�C������������̒�������������ōs�������܂��B
��ł���Ɩ{�����x���W���s�̓��B
�S�z�Ȃ̂��V�C���������B
�\��ł͌ߑO���͉J�͍~��Ȃ��炵�����u�Ƃ���ɂ��ɉJ�c�v�ȃj���A���X�Ȃ��ǁA�I�b�T�����Z��ł�ꏊ���āu�Ƃ���ɂ��v�ɓ��Ă͂܂邱�Ƃ������B
���ԂԌo�߂ƂƂ��ɓV�C�������Ȃ��Ă����낤����A�Z���Ԃ̏������o�傷��B
���Ԃ𑆂��o�����������������āA����ʼnJ���~������V�����ɂȂ��ȁB
������ɏo��Ɖ����m��l���������������B
��H�Ȃɂ��̐l�B�H���Ǝv���Ă���A�}�C�A�~�̗L���������������Ń��W�I�̑����n�܂����B
���`�A�����������Ƃ��I�ǁ`��Ń����c���������ҒB����Ȃ킯���B
�ċx�݂Ƃ����Ə��w�����������Ă���ǁA���ʂ̋x�݂͍���҂���Ȃ̂ˁB
���炭���߂Ă������A���̗x��̐U��t�����đS�R�ς���ĂȂ��B
�`���I�ȍՂ肶��Ȃ�����A�����ƌ���Ƀ}�b�`���������ƐU��t���ɂ�������̂Ɂc���Ǝv�����B
���Ƃ��ƃ��W�I�̑��́A�V��j���������Ȃ��s���A�����悭�^�����ʂ������炷���ɂ̑̑��炵���B
������A���W�I�̑���Q�͐E������ɍ��ꂽ���̂ŁA��P�����^�����x�͂���ɍ����_�C�i�~�b�N�ȓ����������炵���B
�������A���̑�Q��x���l���Ăǂꂭ�炢����낤�H
�I�b�T�����S�R��Q�͒m��A�قƂ�Ǖ��������Ƃ��Ȃ��Ǝv���B
�܂��Ă��荂��x�ȑ�R�܂ł������A���C�f�B�I�̑�����ׂ��ł���B
���Ԃ𑆂��Ȃ���]�����W�I�̑��Őg�̂��ق����Ă���ƁA�����������n�Ɍ������B

�����n���Ė{���ɖ��ʂ��Ȃ��ˁ`
��N�͉͐�~�����ɒނ��܂ōs�������ǁA���N�͒�h���H�����Ă邩�牓��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�I�b�T�����s���ނ��͍H�����肾�ȁc
����ƃ|�C���g�ɓ����B
�����͑O��Ɠ����|�C���g�Ȃ��ǁA�{���̃e�[�}���G�r�͒ނ��悤�ɂȂ������H�Ȃ̂ŁA�����|�C���g����Ȃ��Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ�����ˁB

�܂����̃|�C���g�ւ���Ă���
���ʂ��m�F����ƁA�v���������Ⴂ�B
�{���͑咪�ŁA���ꂩ��݂�݂邤���ɒ��������Ă䂭����A�ނ肪�o������ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�v�������������Ⴍ�ł�I�b�T��
�܂��͊Ƃ̏����B
�O��͐���̃����A���������āA�s�{�ӂȈ�{�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�̂ŁA�{���̓`�����ƃ����A����t���Ă����B

�����A���t�������I
�d�|�����Z�b�g���āA�����ނ邼�I�̑O�ɐ������`�F�b�N�B

�����v���d�|���Ɏ��t���Ē��߂Ă���
�������ׂĒނ��悤�ɂȂ�ȁH
�����ނ��ɗ�������Ă����A�����W�Ȃ��ނ肷���`���������I
�u�c�u�c�Ƃ茾�������Ȃ���A�~�~�Y�G�T�̏����Ɏ��|����B
���͂��̃G�T���S�z�B
��T�G�r�ނ�ɗ�����肾��������A���̑O�Ƀ~�~�Y���ق������ė��āA�����Ƃ��̂܂܂̓z�B
���ꂪ�C�\����������Ƃ����Ɏ��ł��āA�ُL������Ă�낤�ȁc
���鋰��^�b�p�[�̃t�^���J���Ă݂邪�A�L���͂��Ȃ������B
�y���@���Ă݂�ƁA�����ƃY�~�~�l�͐����Ă����I
�����`�A�~�~�Y���Đ����͂���ȁI

�݂�Ȗ��Ȃ������Ă����I
�Ƃ͌����A�݂����ɂ��邩�琶���W�Ȃ����ǂˁB

�ʂɐ����Ă�K�v�����Ȃ�
������19���ŁA�O���17�����������班���͏オ���Ă��邪�A�R���Œނ��̂��ǂ����͕�����Ȃ��B

19���B�����炻�ꂪ�ǂ������I
�e�i�K�G�r�ނ�̏���������������19�����B
��Œނ�J�n����I
����ƃe�i�K�G�r���ނꂽ��`
�܂��͎��у|�C���g�ֈ�{�ڂ𗎂Ƃ��B
���̊Ԃɓ�{�ڂ̉a�t�����������A���������̂Ńu���b�N�t�@�[�X�g���B
���O���O���Ȃ����������n�����A�V�C���������炩�A�����������̂��A�L��ȃe�i�K�G�r�ނ�̐��n�ɂ̓I�b�T���ЂƂ肵���Ȃ��B
�h����������GW�ɁA�݂�ȃG�r�ނ�����Ȃ��ʼn����Ă��c�H�h
�w�Ɂ{������=�e�i�K�G�r�ނ�x�Ƃ����}�������v�������Ȃ��I�b�T���ɂ́A���̒ނ��ɒN�����Ȃ����R�������ł��Ȃ��B
�u���b�N�t�@�[�X�g���I���A��{�ڂ̊Ƃ����Ă݂�ƁA�ڈ�̃E�L�������Ă����B
���I�}�Y�C�I�I
�Q�ĂĊƂ��グ�邪�A���x���B
���S�ɍ��|���肵�Ă���B�������E�L�����ŁB
���Ԃ�nj^�̃_�{�n�[�ɁA�d�|����傫�������čs���ꂽ�Ǝv���B
�E�L�����ʂ���o�Ă���ΐj���������Ȃ邾���ōςނ��Ƃ��������A�E�L�������Ă��Ȃ��̂̓��o���B
�s�N���Ƃ������Ȃ��̂ŁA���S�ɃE�L���ō��|�����Ă��鎖�ԁB
�v�`���I
�����Ȃ��Ă͂ǂ����悤���Ȃ�����A������邵���Ȃ��B
�J�n�ꔭ�ڂŃE�L���疳���Ȃ鍪�|����ŁA�����K�b�N�����B
���̂悤�ɁA�������炩���ɂ��߂��ăO�C�O�C�����Ă������܂܂ɂ��Ă����Ƃ����Ȃ�܂��B
������u���ƂƂ͌����A�E�L�̓������`�F�b�N���Ȃ������܂�ɂ������Ă������悤�Ȃ�Ƃ��y�������グ�āA����̐��̂��`�F�b�N����ׂ��ł��B
�d�|������蒼���A�ēx�����B
������{�̊Ƃ��グ��O�O���I�Ɛj�|���肵�Ă���ǁA���̈����͖��炩�ɓz���B

�_�{�n�[�B������`�I
�͂��A���T���_�����ȁc�B�������ނ���I�b�T���B
�������A�O��Ƃ͈Ⴄ�̂��A�^���ė���̂��_�{�����ł͂Ȃ����ƁB
�e�i�K�G�r���˂��ė��Ă�I
�_�{�n�[�Ƃ͈Ⴄ�A�ׂ����U���̃e�i�K�G�r���L�̃A�^��������B
�ł��A���������ď����߂̃_�{���ȁH�Ƌ^�S�ËS�ɂȂ��Ă���ƁA���鎞�X�`���ƊƂ��グ�����Ƀe�i�K�G�r�p���������B
�����I����I�I
�j�|���肵�Ȃ����ǁA�e�i�K�G�r���˂��Ă��Ă�B
��R���C�ɂȂ�I�b�T���B
���x���G�r�̃A�^���͂�����ǁA�Ȃ��Ȃ��j�Ɋ|����Ȃ��B
�������c�A�܂��G�r���������̂��c
�R�����A�J���V�a�������炽�Ԃ�|����낤���ǁA�~�~�Y�a���Ƃ܂��傫���ĉa������˂��Ă邭�����B
���炭����Ȃ���肪���������A���ɂ���ė����I
���鏬���Ȍ��Ԃɗ��Ƃ��ƁA�����ɃE�L����������B
���̔����͂܂��_�{���ȁc
���҂��Ȃ��ł��炭�u���Ă���A�X�`���ƊƂ��グ�ĕ����Ă݂�ƃr�N���r�N���I�ƃe�i�K�G�r�̔������I
�������`�I�I
����������Ȃ�`���Ɗ肢�Ȃ���A������o�Ă����͍̂��G��ꍆ�̃e�i�K�G�r�N�B

����ƒނꂽ��`�I�I

10cm��Ƃ��̎����ɂ͂܂��܂��̃T�C�Y
����ƃe�i�K�G�r�̊炪����Ċ������I�b�T���B
�����R���Ŗ������������ǁA�܂��J���~�肻�����Ȃ����班���S��B
����Ƃ����ɂ������I
���͂�������������o�Ă��Ȃ��āA���C���u���C�N���邩�ȁH���炢�ɔS��������B
��U�͊��S�ɍ��|���������NJɂ߂�Ɣ������邩��A���炭�����Ă����Ė��f�����Ƃ���Ŕ����グ���B

�Ȃ��Ȃ��S������C
���̃T�C�Y�ɂȂ�ƁA�j���O���Ă��鎞�Ɏw������ł��邪���̒ɂ݂��S�n�悢�B

���̃T�C�Y�ł悭�撣���Ă��ꂽ���C�ȓz
�����āA�����ɎO�C�ڂ��グ���Ă����B

�R�����炢���f�g���Ŕ������낤��
�咪�����璪�ʂ��ǂ�ǂ�Ⴍ�Ȃ�A�|�C���g�I�т�����Ȃ��Ă����B
��{�����|���胉�C���u���C�N�ŏI�����A���ꂪ���X�g�I�̌�����ނꂽ�̂̓_�{�������B

�G�r���ނꂽ���烈�V�Ƃ��܂��傤�I
���Ƃ����킯��90���Ńe�i�K�G�r�R�C�ł����B

�F���C�ɑ�����ւ��A��ɂȂ���
���ʂ̊W�ł킸��90���̒ލs�ł������A�e�i�K�G�r�̊炪����Ė����������I�b�T���B
���Ԃ�A�J���V�g���Ă�������ƏE���Ă����Ǝv���܂����A�������G�r��ނ�グ�Ă����킢����������A����ł����̂��I
�܂��A�莞�Ԃ�������������A���K��ɂ̓T���u���b�h�������̂ł��炭���߂Ă����B

���̃X�s�[�h�̔n�ɏ���Ă݂����ȁ`
����ƃe�i�K�G�r���ނ�o�����悤�ł��ˁB
�܂�GW���ɃG�r�ނ���\��Ȃ̂ŁA������͂ǂꂭ�炢�ނ��̂����y���݂ł��B
�ނ��ƕ�����A�J���V���������ȁH����Ƃ��T�V���H�͂Ă܂��~�~�Y���I�H
���͍L������肾���A����Ȓ��x�����Ƃ́A�������m�ꂽ�l���ł���B
���̋L���������u2022�N�R��ڂ̑�����e�i�K�G�r�ނ�͂�͂茴���́c�v��