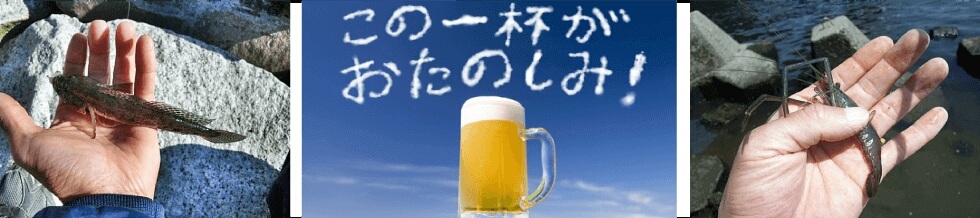2022�N�S��ڂ̑�����e�i�K�G�r�ނ�͂�͂�a����ˁ`
2022�N�T���W��
2022�N�S��ڂ̃e�i�K�G�r�ނ�ɍs���Ă��܂����B
�|�C���g�F������Βn�̑Ί݁i��葤�j
�V�C�F����
�ލs���ԁF7��30���i����150���������j�`10��00���i����131���������Q���j����
�����F20��
�މʁF11�C�@

�ƁF2.1���i�ʕ�U�ƍs�_�����̍��̊Ɓj��2.1���i�V���c�P�u����v�j�@
�����F�t�����J�[�{��1.5���@�n���X�F�i�C����0.3��
�n���F�^�i�S-�ɏ��V�����@�E�L�F���A�ʃE�L�@
�I�����F�K����-�Q�a�@�G�T�F�A�J���V
�d�|���F�n���X�Rcm�̈�{�j
����ł����S��ڂ̑�����e�i�K�G�r�ލs�ɂȂ�܂����B
�����I�ɂ܂������̂ł����A�ނ�Ȃ��킯����Ȃ����i���ă{�E�Y�����Ă邾��I�}�G�I�j�Ȃɂ����I�b�T������邱�Ƃ��Ȃ��ăq�}���B
�����������Ȃ��q�}�Ԃ��B
�܂��A�j���d�|�����͕K�v�ɂȂ邩�犮�S�ɂ̓^�_�ɂȂ�ǁA�ł������莝���̃A�C�e���ōς܂���̂��I�b�T���̃G�r�ނ�̃X�^���X�ł���B
�ނ�a������ߏ��̌����Ń~�~�Y���ق������Ă���n���B
�������A���̂��݂����ꂽ�e�i�K�G�r�ލs�ɂ���肪�������B
�܂������I�Ƀe�i�K�G�r�ނ�ɂ͑����̂ŁA�ނ�Ȃ��Ȃ��Ƃ͌����A�G�r�̃T�C�Y��������܂肵�Ă���B
���ʂ̐l�Ȃ�}�W�}�W�ƃG�r�̌������邱�Ƃ͂Ȃ����낤���ǁA�G�r�̌����ĕ��G�ȑ@�ۂ݂����Ȃ̂ɕ����Ă��āA�o�N�I���Ɖa�ɋ�炢�����Ƃ͂Ȃ��āA���]���]�Ɖa�������Ì��ɉ^��ł��������B
�܂�A�܂��������e�i�K�G�r�ɂ͑����~�~�Y�a�͑傫�߂��āA�a�̎��肾���������������ނ�j�܂Ō��ɓ��炸�A�K�R�ނ�Ȃ��Ƃ������ԂɂȂ�B
����ł��u�܂��A���������Ȃ��q�}�Ԃ������A�e�i�K�G�r�ނ�Ɏv�����ꂪ����킯�ł��Ȃ����c�v���Ǝ����Ɍ����������Ă����B
�������A��͂�ނ�Ȃ��͉̂������I
�O������ނ�̏����ƃ~�~�Y�̍̎�B
�������悩�爤�Ԃ𑆂�����30���B
����ȘJ�͂��₵���ɂ�������炸�{�E�Y���Ƃ��I�H
��������ȁ`�I�Ƒ�����ɐ𓊂����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�܂��ނ�Ȃ������͕������Ă����ł���I
�����ʼn��x�������Ă�悤�ɁA�e�i�K�G�r�Ɖa�̃T�C�Y�̃~�X�}�b�`�B
����A���������Ă����ł͂Ȃ���������A�l�����錴�����ЂƂ��ׂ��Ă䂯�A��������̐����������Ă���n�Y���B
���Ƃ����킯�ŁA�ނ�Ȃ������̍ŏd�v�Q�l�l�̓~�~�Y�Ȃ̂ł���B
�������I�����Ɍ��܂����I������ɈႢ�Ȃ��I�I
�����ŎU�X�~�~�Y�a��ᔻ���Ă���ǁA�u���O���Z�R�����邩��_���Ȃ낤���I�~�~�Y�̂����ɂ���ȁA���̃N�\�n�R�l�����I�I�v���Ċ����ł����ˁB
�������ᔻ����ł̓Y�~�~�l���C�̓łȂ̂ŁA����͉a���`�F���W���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�~�~�Y�ɂ���G��߂𒅂��Ă͂����Ȃ��I
����̉a�̓e�i�K�G�r�ނ�̉����ł����A�J���V���B
�ދ����ŕ��ʂɔ����Ă���ǁA�p�b�P�[�W�͏������Ă����g�͂������������ĂāA�]���̔��ނł��Ȃ�����g���邱�Ƃ��Ȃ��B
���l�i�����̒ނ�a�ɔ�ׂ�Έ������ǁA�I�b�T���I�ɂ̓A�J���V�����̂��߂ɒދ�܂ő����^�Ԃ̂��ʓ|�L�������̂ŁA���܂Ŕ����ɍs���Ȃ������Ƃ������R�ł�����B
�������A�����A�J���V�������ɍs���ƂȂ�Ƃ�͂�ʓ|�������ȁ`
�u���ɉ����������̂Ȃ��ȁ`�H�v���ƍl���Ă�����A�ӂƎv�������B
�u�������I�����E�L�����������I�v
�I�b�T���̓e�i�K�G�r�ނ�ɂ͏������V���̃W���^���ʃE�L���g���Ă���ǁA�i�C�X�T�C�Y�̃_�{�n�[�Ƃ����|����ƃA�b�Ƃ����ԂɌ��[�������čs����A�E�L���ƍ��|���胍�X�g�B
����Ȓ��q�Œn���Ɏ莝���̃E�L�������Ă䂭�c
�Ȃ̂ŁA�ދ�ɍs��������Ƃ��āu�E�L������Ȃ����Ⴞ��I�v�Ǝv�������ǁA�����ł܂��Z�R���l���������ԁB
���`�������A�������邶���H
���܂ł�������Y��Ă����ǁA�e�i�K�G�r�ނ�̃E�L�ɒ��x�ǂ��A�C�e������ʂɗ]���Ă����̂��v���o���B
���̃A���Ƃ̓R����

���a�Wmm�̔��A�X�`���[����
�Ȃ�ł���Ȃ̂��E�`�ɂ���̂��H�Ă�Ō������Ȃ����A���Ԃ�^�R�ނ胋�A�[�̕��͒����Ŕ������Ǝv���B
�ǂ����܂����X�g�������A���̃X�`���[�����ŏ\�������I
���������Ȃ̂Ōu���h���Œ��F���A������ʂ������J�����B

���F�������炵��������
�T�C�Y�����܂Ŏg���Ă����E�L�Ɠ������炢�B

���傤�Ǘǂ����~�̃T�C�Y��
�R�����g��������I�Ȃ��ǁA���Ăǂ�����đ������悤���ȁH
���ʂ̃V�����E�L�݂����ɂQ��ʂ��ł��������ǁA�e�i�K�G�r�ނ�ł͌��ɐ����ăE�L�������|������A�������O�B�I�ƈ�������Ɣ��A������鎖�Ԃ��l�����Ȃ����Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA�Ⴄ�����ő������邱�Ƃɂ���B
�p�ӂ���͕̂��ʂ̗փS���B
�܂��̓E�L�ɓ�����ʂ��B

�@�������E�L�̌��ɒʂ�
20cm���炢�ɃJ�b�g�����ʂ̃��C�����E�L�̌��ɒʂ��A�փS���ɂ����点�A�ĂуE�L�̌��ɒʂ��B

�A�ʂ̃��C�����E�L�̌��ɒʂ��A�փS�����o�R���Ė߂�
���̃��C�����������������ėփS�����E�L�̌��ɓ����B
���փS���͂Q�{�Ƃ����ɓ���܂��B

�B�փS�����E�L�̌��ɓ����
���C�����āA�փS���̗]�v�ȕ������J�b�g������o���オ��`

�C�փS�����J�b�g���Ċ���
�R���ňړ������A�ʃE�L�������ł������ǁA������A�E�L�����X�g�����炱�̍�Ƃ�����ł��̂��ʓ|���ȁ`
�܂��A���̎��͂܂��l���悤�I
���̂悤�ɃE�L������^�_�ōς܂��悤�Ƃ����`���P�ȃI�b�T���B
�������A��������̂��l�グ���b�V���̍����B
�I�b�T���̂悤�ȏ����́A���̂悤�ɒ܂ɉ��悤�Ȑߖ�����Ȃ���A���ʂ̐�����������������̒��Ȃ̂ł���B
�O�d��̑�����e�i�K�G�r�ލs
�����̂悤�Ɉ��Ԃ𑆂�����30���B
�{���������̌���ɓ����B
�ʂɂ��̃|�C���g����Ȃ��Ă��������ǁA�����|�C���g����Ȃ��ƃ~�~�Y�ƃA�J���V�̈Ⴂ���r�ł��Ȃ�����ˁ`

�����������̃|�C���g��
�������A�{���͖�肪����B
���Ɏ�����o�����������犴���Ă������ǁA���������������B
������֏o�����͂�苭���ɂȂ��Ă��āA�܂������ˁ`�A�����`�c
�R�������̋������ƒu���Ƃ͕��ɐ����ăe�g���|�b�g���痎�����܂���A�{���͎莝���̈�{�Ƃł�邵���Ȃ��B
���݂̒��ʂ͂قږ����̎��ԑтŁA����������傫�Ȓ��ʂ̕ω��͊��҂ł��Ȃ��B
���Ő��ʂɔg�������Ă��āA�_���̌��Ȃ�Č����₵�Ȃ��I
�w��{�Ɓ�������Ȃ����g�Ō����Ȃ��x�̎O�d�ꂾ���A�����܂ŗ��āu��I�A��܂����I�v�����イ�킯�ɂ������Ȃ��̂ł�邵���Ȃ��B

���Ȃ茵���������ł���
����p�ӂ������A�ʃE�L�̃f�r���[��B

�܂��A�g����낤�āc
�܂��͍P��̐��������͐�T�Ɠ�����20���������̂ŁA�ނ�Ȃ��킯�ł��Ȃ��̂��ȁH

20���͒ނ�Ȃ����Ȃ������Ȃ̂��ȁH
�ł͑����A�J���V�a�ɂāI���Ǝv�������ǁA�A�J���V��j�ɑ�������̂Ɏ肱����B
�I�b�T���̘V�Ⴊ�i�s���Ă���̂ŁA�ׂ��������a�͎苭�����I
���܂��Ƀn�����ɏ������I�I

�A�J���V���Ă���Ȃɍׂ����������������H
�悤�₭�j�ɒ����Z�b�g���A�O��̎��у|�C���g�ɗ��Ƃ����Ƃ��邪�A�����Ŏd�|���������đ_�����t���Ȃ��B
�}�W���I�H
���傤���Ȃ��̂ŃI�����̃K���ʂ���������ʂ��ďd�ʂ𑝂₷�B
�d�|���𗎂Ƃ����A���ʂ����̗����g�ōr��Ă���̂ŃA�^�����S��������I
�Ȃ̂ŁA�E�L�͑S���A�e�ɂȂ�Ȃ��B
�������������^�C���ނ��ɂȂ�B
�^�C���ނ���Ă����̂̓I�b�T��������ɕt�������ǁA���̍�Ƃ̐������̂��Ă���̂��ȁH
�v�́A������̎��ԋ�킹�Ă����āA���̎��ԂɂȂ�����Ƃ��グ�ĕ����Ă݂�Ƃ����ނ���B
�ʂɒ������ނ������Ȃ��āA���낢��Ȓނ胂�m�ł������ʂɂ���Ă��ƁB
�w�q����40�@�R�`20�x�Ƃ��͕��������Ƃ������������Ǝv���܂��B
���݂ł͎d�|�����ނ�����Ⴄ����R���͓��Ă͂܂�Ȃ��炵�����ǁA������̎��Ԓu���ĕ����グ�Ă݂�Ƃ����ޖ@�ɂȂ�܂��B
����̂��̏ꍇ�͏����Ӗ��������Ⴄ���ǁA�܂������悤�Ȃ��ȁH
�Ȃɂ��E�L�ނ�Ȃ̂ɃE�L���A�e�ɂȂ�Ȃ�������A���`���邵���Ȃ��B
�~���N�ނ�ɂ���ׂ����H�Ƃ��v�������A���̋����ŊƂ������邩��~���N����肭�����낤�āc
���݂̍j�̎��у|�C���g�͑S�ċ�U��ɏI���A�n�e�H�ǂ��������c
�A�^��Ȃ���ɁA���̒ނ�Â炢�B
�܂����������{�E�Y�m��H�Ŕw�Ƀc�c�[���Ɨ₽�����̂�����A�����̒ލs�͖����������̂ɂ��āA�Ƃ��ƂƋA�邩�H�Ƃ��������̋C���������N���N�Ɗ������������B
�������A�喇�͂����čw�������A�J���V�̂��߂ɂ��A�����ăY�~�~�l�̉�����ԏシ�邽�߂ɂ��A�����Ă��̃u���O�̕Ў�Ő�������ǎ҂̂��߂ɂ��G�r��ނ�˂Ȃ�Ȃ��I
��͂茴���̓A���^��������c
�ڂ��Â炵�ăe�i�K�G�r���t���Ă������Ȍ��Ԃ������A�d�|���𗎂Ƃ��B
�J�n30���Ԃ͂ȁ`��������Ȃ��āA�S���܂ꂻ���ɂȂ��Ă������A����|�C���g�ł���Ɛ����������������B
�e�i�K�G�r�̔������ۂ����ǁA�����������ʋ߂��܂ʼna�ɕt���Ă��ē���������A�������̃|�C���g�ɂ͖߂��ĂȂ����ȁH
�Ƃ��グ�Ă����ɉa�𗣂��܂����̃|�C���g�ɖ߂���ǁA���̂悤�ɐ��ʋ߂��܂ŏオ���Ă����Ⴄ�ƁA���̏ꏊ�ɓ������Ⴄ��ł���ˁ`
���Ҕ��œ����|�C���g�ɗ��Ƃ��Ẵ^�C���ނ�B
���Ԃŕ����グ��ƃr�N���r�N���I�ƃG�r��������I
�オ���Ă����̂͂Tcm���炢�̂��킢���G�r�����B

����ƒނꂽ��`�I

�{�����o�Ԃ��������G�A�[�|���v�w���Ђ��܂̗́x
���������|�C���g����ނꂽ���A��͂�A�J���V�a�͂��̃T�C�Y���E���Ă��܂��B

���������悤�ȃT�C�Y
�A�J���V�a�̓n���|���肪�ǍD������A�������G�r���ނ�Ă���B
�I�b�T���͒ނ肪�I������烊���[�X���邩��A�ł�����蒚�J�ɐj���O�����ǁA����ł��������G�r�͏��V���Ă��܂���������B
�I�b�T�����A�J���V�a���g��Ȃ����R���R���ł�������ǁA�ނ�Ȃ����͒ނꂽ�ق����y��������A�a�̑I���͔Y�܂������肾�B
���̓����|�C���g���珬�����Ȃ�����T�C�オ���Ă��āA�{���̖ڕW���c�����i10�C�j�ɏ���C���B
���Ȃ݂ɖ{���̃^�C���ނ�́A50�b�o�����������肻�`���ƕ����グ�āA��������������A�����ɂ߂���10�b��킹�Ă���Ƃ��グ�������B
���̊Ԃ̓E�L�Ȃ�Č��ĂĂ��Ӗ����Ȃ�����A���`���Ǝ��v�Ƃɂ�߂����B
�I�b�T���͂��������ő̓����v�͂��Ȃ葁���i�ނ̂ŁA�^�C���ނ�̎��͎��v�̓}�X�g�A�C�e���B
���̌�͖Y�ꂽ���Ƀ|�c���|�c���ނ����x�ŁA�ŏ��݂����ɂЂƂ̃|�C���g���畡���C�͖����A��C��C�̏E���ނ�B
�����͕��͋������ǃ_�{���ނ�Ȃ��Ă����ȁ`���Ǝv���Ă���A�����������Ă��₪���āI

�_�{�͂����̂���I�_�{�́I�I
�A�J���V�a���Đj�Ɏh���Ƃ����ɑ̉t�������Ȃ��Ă䂭����A�}���ɉa�ウ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ނ��ނ�Ȃ��ɂ�����炸�a��p�ɂɃ`�F���W���Ȃ��ƒނ�ɂȂ�Ȃ��B
�m���ɃR���͖ʓ|�L�����ǁA��ɐV�N�ȉa�Œނ肷�邱�ƂɂȂ邩��A�����Ĉ������Ƃ���ł��Ȃ��B
�ނ�a�͐V�N�ȕ����ނ��͎̂����̗��B
�ނ��l�͒ނ�邽�тɉa��V�������邩��܂��܂��ނ�āA�ނ�Ȃ��l�͂��܂ݐ��������������Ȃт��a�����`���ƕt���Ă邩��S�R�ނ�Ȃ��B
�ނ��ł͂悭���镗�i���B
�l�Ԃ����č�肽�Ă̗����Ƃ����łȂ�����������ł���A�V�N�ȕ���I�Ԃł���H
�������ē����ł��B

�̉t��������Ɣ炾���ɂȂ邩��ނ�Ȃ��Ȃ�
���鎞�A������Ɛ[�߂̃|�C���g�ŕ����グ��Ƃ�艜�̕��ֈ�������ꍪ�|�����B
�u���ꂽ�I���������Ɉ�������Ηǂ��������ȁc�v���Ƃ��炭�ɂ߁A�z�������o���̂�҂B
�䖝��ׂ��������ǁA�z���������̂ł��̏u�Ԃɔ����グ��ƁA�����C�`�̃e�i�K�G�r���オ���Ă����B

�����ėǂ������I

�ł�13cm���ĂƂ��납�c
���������̒ނ��ɂ̓I�b�T���ЂƂ�c
�Ί݂ɂ�16�ʁi���������ȁH�j�̍L��Ȗ싅�ꂪ����A�ɂ��₩�Ȑ����������Ă���B
�q�ǂ������̊撣���Ă��鐺�ɍ�����A������A�ēȂ̂��R�[�`�Ȃ̂��̓{�����͂������I�̂悤�ɋ����B
�u������`�I�Ȃɂ���Ƃ�႟�`�`�`�I�I�v
�Ȃ�Ŗ싅�̎w���҂��Ă���Ȃɓ{��낤�H
�A���͋����Ă��Ȃ��āA�����̕s�@�����q�ǂ��ɂԂ��Ă邾���Ȃ�ˁH
�݂�Ȃ��݂�Ȃ���Ȃ��낤���ǁA�싅�ɂ͔����I�^�C�v�̃R�[�`�������C������B
�A������q�ǂ����y�����Ȃ��Ƃ��낤�ȁ`���Ǝv�����ǁA���{�̖싅����WBC�łQ����D�����Ă��邵�A���W���[�Ŋ��Ă���I�����������A���ʂ͏o�Ă��ȁ`
����ȑI�肽���̎w���҂������I�^�C�v�������̂��͒m��ǁA�v���싅�I�肽���́u�w������̊ē͕|�������I�v�Əq������̂���������A��͂蔚���I�������낤�ȁ`
�Ί݂ɂ͋��炭1,000�l�͂���ł��낤�Ǝv������₩���Ƃ͑ΏۓI�ɁA���̍L��Ȓނ��ɂ̓I�b�T���ЂƂ�c
�����ɐ�����A�ǓƂ����ݒ��߂Ȃ���̃������[�t�B�b�V���O�c
���ǁA�Q���Ԕ��S����11�C�ƖڕW�B���Ŗ��������B

�c�����������烈�V�Ƃ��܂��傤�I
�O��͂��R���ゾ���A�|�C���g�����ԑт������A�����������B
�����������ŃA�^���������炸�A�����قƂ�Ǔ������A��������{�Ƃł��c�����Ȍ��ʁB
��͂��ނ�Ȃ����������͉a�������A�Ƃ������_�ŊԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B
���܂�I�Y�~�~�l�B
��͂茴���̓A���^��������I
���̏ꍇ�́c
���̋L���������u2022�N�T��ڂ̑�����e�i�K�G�r�ނ�͂��낻�낢���J���ˁv��